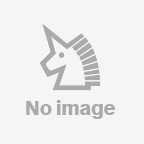今日は肌寒いです。風も冷たいので、なんとなく出不精。
昨日は、朝方まで雨が降っていたので、久しぶりに食料釣師になってみました。
しかし釣果はこれだけ。

上がイワナ、下3匹がヤマメです。切り詰めて2日分?
釣具屋のオヤジ曰く、「爆釣だよ」「みんな自粛しているから」。
期待してたんですがねええ。魚も自粛しているのかしら?
※福島の釣りは今が穴場かも?ちょっと前に見たいわきの人のブログでは、爆釣だったとか。
●自粛って言葉の意味は?
「千葉県は26日、国の暫定規制値を超す放射性物質が検出され出荷の自粛・制限対象となった同県香取市産ホウレンソウ・・・」<読売新聞から一部転載>
これ出荷されちゃったのね。
なぜ「禁止」って言葉を使わないんでしょう?
虹を7色で表現するのは日本だけ。他国では3~4色でしか表現できないんだとか。
多彩な表現方法がある文化も好きだけど、同時に曖昧さも同居しているんですよね。
ちゃんと使い分けしてほしいなあ。
帰りに塩ビ管を買ってきました。
地震後の排水の水漏れを直すためです。

地表から水が染み出しています。左下に排水口があります。
出口側半分は竹で繋いでいたのが、振動でずれてしまったようです。
竹は傷んでたので、取り替えました。

竹を取りに行く手間と、1200円出費するのと、どっちを採るか?
塩ビ管のほうが便利なのね。ボクにもちょっとだけユトリがあったのでした。

 参考になったらクリックお願いします。
参考になったらクリックお願いします。
★オマケ
ふつうならここで終わりたいのですが、どうも頭が飽和しているので吐き出しておきましょう。
ここ1か月半、ボクなりにアチコチ動き回っていました。
そこでいろいろな人に会いましたよ。
●直接被災した人にも会いました。(親戚にもいますが)
こんなときは何にも言う言葉がないですね。
言葉に詰まるあまり、ヘンな冗談を言っちゃって、気まずくなったことも経験しましたよ。
原発周辺では、興味深い反応が見られました。20キロ圏外~50キロくらいの方たちです。
●田舎への移住者の方たちは、すばやく避難した人が多いようです。翌日とか最初の水素爆発があったときです。
その後の事態の様子をみて、戻って来てる人もいますが、そのまま避難続けている人もいます。
これは、あらかじめ知識があった人と、元の巣が有る人、もともとフットワークのいい人、のような気がします。
●地元の人たちは動いていないですね。
「移住者は逃げ足が速いよなあ。俺たちは行くとこがないんだから」ちょっと皮肉交じりの言葉も聞きましたね。
自分の土地を捨てるわけにはいかないって心情のような気がします。
しかし、ネットなどでの情報収拾できている人は非常に少ないです。もし、知っていたらどうしたんでしょうねえ。
●30キロくらいでも、まったく動かない移住者もいました。
腹が座っているのか、ちゃんとした知識があるのか、リスクを承知なのか?
最後のような気がします。
●しばらく様子を見てから避難した人
1週間ほど経って、安定ヨウ素剤などが配布されたり、周囲が動いたために吊られて(恐怖感を覚えて)避難した人もいます。
しかし、子供の学校が始まるとか、仕事をしなければならないとの理由で、10日ほどで戻ってきた人もいます。
避難先での気まずさってのもあるようです。
この方たちも、ネット情報は少なかったですね。
●1か月くらい迷った挙げ句、避難を決断した人
仕事の関係でもないので、何を迷っていたのかは不明です。
ネットなどでの情報を集めるにしたがい、徐々に子供のことが心配になったようにも思います。
●単純に放射能と聞いただけで、パニクって避難してしまった人もいました。
普段は張り切っているんですが、こんなとき人間は、いろいろな表情を見せますね。
ボクは、ふだんの情報収集は、テレビの音声とネットが中心です。まあ、映るテレビや新聞はないのですから。
ネットのニュースは日課です。何かひっかると、ネットで調べてますね。
「シーベルト」って単語が出てきてからは、かなり調べましたよ。実にたくさんの情報があって混乱もしてますがね。
一般の情報はあまりにも抽象的だったので、調べたわけですが、知れば知るほど、客観的に物事を見てしまいますね。これは、ある意味、人の心情を受け取る感情が薄れてしまうって欠陥もあるようです。
●一般メディアやネットでもわからないこと
先日、神奈川から友達がやってきました。
「ネットなどでも調べたけど、いまいち周辺状況がわからないんだよね」って言ってました。
「被災地から20キロも離れると、ほとんど平常に戻ってるよ」というとすごく驚いていました。
行ってもいいもんだかどうか、すごく不安だったんだそうです。
●現場一見
友達が持ってきた災害写真集なるものを見ました。一般メディアに載っていないような、衝撃的な写真が載っていました。
しかし、この写真集もテレビの映像も新聞も、第三世界の出来事のように映りますね。
友達はボランティアも考えて来たようですが、今回は、結局、現地を見て言葉を忘れ、絶望感を味わって帰りましたよ。この体験は次の一歩になるのでしょうね。
実際に現場を見ることが一番体感できます。
不謹慎かもれませんが、被災地見学ツアーってのがあってもいいんじゃないのかな?
第三者的でなく、ニッポンを真剣に考えるキッカケになると思うのですがねエエ。
●郡山の学校の汚染された土は?
取り除くのはいいとしても、どうやって処分するのか興味があったのだけど、結局処分できないのね。
タダのゴミとして処分場に捨てるというのを住民が反対したそうですね。
これが行政ですからねええ・・・。
チェリノブイリでも菜の花を植えて、吸収させて、燃やして、灰を隔離処分するって実験を今でもやっているらしいです。今でもですよ。
それなりに効果はあるようですが、この対処方法が見つからないと、かなり広い部分が管理地域(立ち入り禁止)になってしまいますね。
どうも、このあたりの情報がはっきりわかりません。
知り合いの「たくさん」のブログにこんなのがありました。
●ニッポンには昔から放射能がいっぱい
気象研究所地球化学研究部が大気圏の人工放射性核種の濃度変動の1955年ころからの観測データというもの。
つまり、ソ連やアメリカや中国が原爆実験したためその後の経過を現在も調べているということですね。
1990年以降から現在までは安定しているので、これを1とすると、若干大雑把な平均値だけど、
1980年代は、10倍
1970年代は、100倍
1960年代は、1000倍もあったのです。
単純に考えてはいけないのかもしれないけど、現在の平常時の平均レベルを0.02μS/hとすると、
1980年代は、0.2μS/h(年間1.8mS) →30歳代の人が生まれた。
1970年代は、2μS/h (年間18mS) →40歳代の人が性まれた。
1960年代は、20μS/h (年間180mS) →50歳代の人が生まれた。
になっちゃうのね。
50代の人、子供のころは影響が大きいっていうから心配ですねえ。(心配ならちゃんと調べてね)
<こう解釈していいのかしら?たくさん!>
●年間100mSで、1万人に50人がガンのリスクがあるって話
この数値、どう考えるか、受け止めるかだねええ。
つまり0.5%なんだけど、書き方によって雰囲気が違うのね。
1億人だと50万人?
1987年のガン患者数は約50万人だって。ってことは、現在50歳の方が30歳くらいのころですね。
それ以降増えて130万人くらいになってます。
もしかしたら関係あるんでしょうかねえ。
しかし、これまでも日常的にガンの情報は受け入れているわけだから、なんの心配もないって受け止めることもできますね。
やれやれ、また、とりとめもなく、書いてしまった。これ自己満足かしら。
昨日は、朝方まで雨が降っていたので、久しぶりに食料釣師になってみました。
しかし釣果はこれだけ。

上がイワナ、下3匹がヤマメです。切り詰めて2日分?
釣具屋のオヤジ曰く、「爆釣だよ」「みんな自粛しているから」。
期待してたんですがねええ。魚も自粛しているのかしら?
※福島の釣りは今が穴場かも?ちょっと前に見たいわきの人のブログでは、爆釣だったとか。
●自粛って言葉の意味は?
「千葉県は26日、国の暫定規制値を超す放射性物質が検出され出荷の自粛・制限対象となった同県香取市産ホウレンソウ・・・」<読売新聞から一部転載>
これ出荷されちゃったのね。
なぜ「禁止」って言葉を使わないんでしょう?
虹を7色で表現するのは日本だけ。他国では3~4色でしか表現できないんだとか。
多彩な表現方法がある文化も好きだけど、同時に曖昧さも同居しているんですよね。
ちゃんと使い分けしてほしいなあ。
帰りに塩ビ管を買ってきました。
地震後の排水の水漏れを直すためです。

地表から水が染み出しています。左下に排水口があります。
出口側半分は竹で繋いでいたのが、振動でずれてしまったようです。
竹は傷んでたので、取り替えました。

竹を取りに行く手間と、1200円出費するのと、どっちを採るか?
塩ビ管のほうが便利なのね。ボクにもちょっとだけユトリがあったのでした。
★オマケ
ふつうならここで終わりたいのですが、どうも頭が飽和しているので吐き出しておきましょう。
ここ1か月半、ボクなりにアチコチ動き回っていました。
そこでいろいろな人に会いましたよ。
●直接被災した人にも会いました。(親戚にもいますが)
こんなときは何にも言う言葉がないですね。
言葉に詰まるあまり、ヘンな冗談を言っちゃって、気まずくなったことも経験しましたよ。
原発周辺では、興味深い反応が見られました。20キロ圏外~50キロくらいの方たちです。
●田舎への移住者の方たちは、すばやく避難した人が多いようです。翌日とか最初の水素爆発があったときです。
その後の事態の様子をみて、戻って来てる人もいますが、そのまま避難続けている人もいます。
これは、あらかじめ知識があった人と、元の巣が有る人、もともとフットワークのいい人、のような気がします。
●地元の人たちは動いていないですね。
「移住者は逃げ足が速いよなあ。俺たちは行くとこがないんだから」ちょっと皮肉交じりの言葉も聞きましたね。
自分の土地を捨てるわけにはいかないって心情のような気がします。
しかし、ネットなどでの情報収拾できている人は非常に少ないです。もし、知っていたらどうしたんでしょうねえ。
●30キロくらいでも、まったく動かない移住者もいました。
腹が座っているのか、ちゃんとした知識があるのか、リスクを承知なのか?
最後のような気がします。
●しばらく様子を見てから避難した人
1週間ほど経って、安定ヨウ素剤などが配布されたり、周囲が動いたために吊られて(恐怖感を覚えて)避難した人もいます。
しかし、子供の学校が始まるとか、仕事をしなければならないとの理由で、10日ほどで戻ってきた人もいます。
避難先での気まずさってのもあるようです。
この方たちも、ネット情報は少なかったですね。
●1か月くらい迷った挙げ句、避難を決断した人
仕事の関係でもないので、何を迷っていたのかは不明です。
ネットなどでの情報を集めるにしたがい、徐々に子供のことが心配になったようにも思います。
●単純に放射能と聞いただけで、パニクって避難してしまった人もいました。
普段は張り切っているんですが、こんなとき人間は、いろいろな表情を見せますね。
ボクは、ふだんの情報収集は、テレビの音声とネットが中心です。まあ、映るテレビや新聞はないのですから。
ネットのニュースは日課です。何かひっかると、ネットで調べてますね。
「シーベルト」って単語が出てきてからは、かなり調べましたよ。実にたくさんの情報があって混乱もしてますがね。
一般の情報はあまりにも抽象的だったので、調べたわけですが、知れば知るほど、客観的に物事を見てしまいますね。これは、ある意味、人の心情を受け取る感情が薄れてしまうって欠陥もあるようです。
●一般メディアやネットでもわからないこと
先日、神奈川から友達がやってきました。
「ネットなどでも調べたけど、いまいち周辺状況がわからないんだよね」って言ってました。
「被災地から20キロも離れると、ほとんど平常に戻ってるよ」というとすごく驚いていました。
行ってもいいもんだかどうか、すごく不安だったんだそうです。
●現場一見
友達が持ってきた災害写真集なるものを見ました。一般メディアに載っていないような、衝撃的な写真が載っていました。
しかし、この写真集もテレビの映像も新聞も、第三世界の出来事のように映りますね。
友達はボランティアも考えて来たようですが、今回は、結局、現地を見て言葉を忘れ、絶望感を味わって帰りましたよ。この体験は次の一歩になるのでしょうね。
実際に現場を見ることが一番体感できます。
不謹慎かもれませんが、被災地見学ツアーってのがあってもいいんじゃないのかな?
第三者的でなく、ニッポンを真剣に考えるキッカケになると思うのですがねエエ。
●郡山の学校の汚染された土は?
取り除くのはいいとしても、どうやって処分するのか興味があったのだけど、結局処分できないのね。
タダのゴミとして処分場に捨てるというのを住民が反対したそうですね。
これが行政ですからねええ・・・。
チェリノブイリでも菜の花を植えて、吸収させて、燃やして、灰を隔離処分するって実験を今でもやっているらしいです。今でもですよ。
それなりに効果はあるようですが、この対処方法が見つからないと、かなり広い部分が管理地域(立ち入り禁止)になってしまいますね。
どうも、このあたりの情報がはっきりわかりません。
知り合いの「たくさん」のブログにこんなのがありました。
●ニッポンには昔から放射能がいっぱい
気象研究所地球化学研究部が大気圏の人工放射性核種の濃度変動の1955年ころからの観測データというもの。
つまり、ソ連やアメリカや中国が原爆実験したためその後の経過を現在も調べているということですね。
1990年以降から現在までは安定しているので、これを1とすると、若干大雑把な平均値だけど、
1980年代は、10倍
1970年代は、100倍
1960年代は、1000倍もあったのです。
単純に考えてはいけないのかもしれないけど、現在の平常時の平均レベルを0.02μS/hとすると、
1980年代は、0.2μS/h(年間1.8mS) →30歳代の人が生まれた。
1970年代は、2μS/h (年間18mS) →40歳代の人が性まれた。
1960年代は、20μS/h (年間180mS) →50歳代の人が生まれた。
になっちゃうのね。
50代の人、子供のころは影響が大きいっていうから心配ですねえ。(心配ならちゃんと調べてね)
<こう解釈していいのかしら?たくさん!>
●年間100mSで、1万人に50人がガンのリスクがあるって話
この数値、どう考えるか、受け止めるかだねええ。
つまり0.5%なんだけど、書き方によって雰囲気が違うのね。
1億人だと50万人?
1987年のガン患者数は約50万人だって。ってことは、現在50歳の方が30歳くらいのころですね。
それ以降増えて130万人くらいになってます。
もしかしたら関係あるんでしょうかねえ。
しかし、これまでも日常的にガンの情報は受け入れているわけだから、なんの心配もないって受け止めることもできますね。
やれやれ、また、とりとめもなく、書いてしまった。これ自己満足かしら。
- 関連記事
-
-
 メモリー増設でストレス解消か
2011/08/25
メモリー増設でストレス解消か
2011/08/25
-
 免許更新、保険請求、網戸張りのこと
2011/08/06
免許更新、保険請求、網戸張りのこと
2011/08/06
-
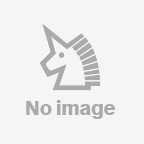 風評?被害者
2011/06/18
風評?被害者
2011/06/18
-
 こんなところにも震災被害が
2011/05/12
こんなところにも震災被害が
2011/05/12
-
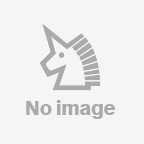 いわき市議のブログ●原発震災の元凶と生きる権利●
2011/05/06
いわき市議のブログ●原発震災の元凶と生きる権利●
2011/05/06
-
 震災人間模様など
2011/04/29
震災人間模様など
2011/04/29
-
 ミツバチ建屋1~4号機と黄色いハンカチ
2011/04/16
ミツバチ建屋1~4号機と黄色いハンカチ
2011/04/16
-
 伝え方のヒント
2011/04/09
伝え方のヒント
2011/04/09
-
 余震6強・またまた無事です(+追記)
2011/04/08
余震6強・またまた無事です(+追記)
2011/04/08
-
 緊急地震速報の憂鬱
2011/03/28
緊急地震速報の憂鬱
2011/03/28
-
 食料調達に遠征しました
2011/03/20
食料調達に遠征しました
2011/03/20
-
最終更新日 : -0001-11-30